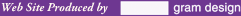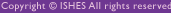社会的処方(Social Prescribing)
現代社会では、「医療機関に持ち込まれる問題の2-3割は社会的な問題」と言われるほど、社会的孤立、ストレスの多さ、地域社会の変化などにより、健康や福祉の課題が複雑化しています。病気の診断や治療だけでは解決できない問題が多く、孤独感やストレスが原因で健康を害している場合、薬だけで解決できないケースも少なくありません。
こうした背景から注目されているのが「社会的処方」という考え方です。社会的処方は、医療や福祉の専門職などが、患者の社会的課題に対応するために地域社会のリソースを紹介・活用するアプローチです。英国を中心に発展したこの考え方は、患者の社会的・心理的ニーズに応じて、多様な支援を提供することを目的としています。
社会的処方の仕組み
社会的処方の実施には、医師や看護師、ソーシャルワーカーといった専門職だけでなく、地域のNPOやボランティア団体も関わります。具体的には、次のようなプロセスで進められます。
- 1. 医療機関での相談: 患者が不調や悩みを訴えると、医療スタッフが社会的処方の必要性を判断します。
2. リンクワーカーとの面談:リンクワーカーと呼ばれるコーディネーターが、患者の状況やニーズをヒアリングし、適切な地域資源(地域のサークルなど)を紹介します。英国ではリンクワーカーの養成が制度化されています。
3. 社会活動への参加:趣味のサークル、運動教室、ボランティア活動といったプログラムに参加することで、社会的なつながりを作り出します。
社会的処方の効果と可能性
社会的処方が目指すのは、単に症状を緩和するだけではなく、「生きがい」や「幸せ」を実現することです。例えば、孤独感を和らげる活動を通じて、メンタルヘルスが改善されるケースが多く報告されています。また、地域の運動プログラムへの参加は、生活習慣病の予防やうつ病、認知症の発症リスクを下げるだけではなく、楽しみにつながります。
英国では、2010年代からNHS(国民保健サービス)が積極的に社会的処方を導入しています。調査によると、医療機関の受診回数が減少し、医療費削減にもつながることが確認されています。
日本でも、社会的処方の導入を試みている団体が複数あります。社会的処方は、医療だけでは解決できない社会的課題に取り組む新しいアプローチです。医療と地域資源を橋渡しすることで、患者一人ひとりの生活の質を向上させることが期待されています。